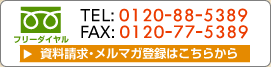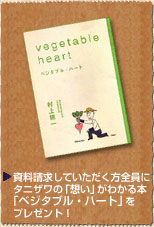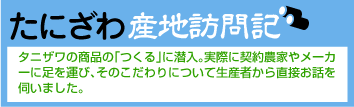桃農家中沢農園訪問記(前編)
今回は、桃農家の中沢義直さんを紹介したいと思います。
中沢さんは、毎年美味しい桃を出荷して下さっています。
6月5日(土)に、中沢さんの桃の生産地、山梨県笛吹市を訪問しました。
以下の文章は、参加した社員のレポートです。
前編と後編に分かれた長編となっていますが、ご覧になってみてください。
今回は、前編です。
<一年に一度しか試せない>
うす曇の天候の中、私たち一行7名は、中央高速を車で下って、
午後4時半頃に山梨県笛吹市(旧一ノ宮町)にある桃農家の
中沢義直さんのお宅に到着した。
奥様の出迎えを受け、お宅で少し待っていると、
程なく中沢さんが畑から戻られた。
数年前にもお会いしたが、健康的に日焼けして、
笑うと歯並びのいい白い歯が印象的な人だ。
改めて、自己紹介をすると、恒例にもなっているが、
新入社員(今春入社の3名)の出身地を興味深く聞かれた。
中沢さん:「この中に地方出身者はいるかな?」
3人のうち島根出身のH君に白羽の矢が当たる。
中沢さん:「島根といえば尼子家だ。島根の尼子家といえば、
『我に七難八苦を与えたまえ』
と言った武将がいたなぁ。なんと言ったっけ。」
ここで、歴女(注1)ならぬ歴男のT部長が、
「『山中鹿之助』ですね。」とやや控えめに答える。
(注1)歴女(れきじょ)は、歴史好きの女性を指す造語。
中沢さん:「そうそう。山中鹿之助だ。」
(ふむ、打ち合わせなしにこの二人の会話はすごい・・・ブログ筆者)
という話になり、昔の人はそこまで言って自分を厳しいところに
追い込んでことに臨んだが、今の人間は昔の人に比べて軽くなってきた
という中沢さんの現代人評がしばし続いた。
そのような話のプロローグから、最近の桃作りの本題に話が進んだ。
もう50年農業を続けている中沢さんが、
最近は今までの勘や、経験が通用しないとのこと。
ベテランの中沢さんも最近の気象の変化には困惑されているようだ。
中沢さん:「(試したいことがあっても)一年に一度しか試せないんだ。」
この一言に、果樹園農家としての中沢さんの思いと、常に前向きな向上心を感じる。

<今年の桃栽培について>
今年は、中沢さんによると、1月、2月の気温が高く、
通常桃の開花は4月10日頃なのに3月下旬に花が咲いてしまったそうだ。
4月になると、今度は冬に逆戻り、遅霜があったり、氷が張ったりした。
5月は、気温が乱高下して10℃から25℃の温度差があった。
日照が少なく、生育が遅れたとのことだった。
このような、いわば異常気象のときに中沢さんが
一番気をつけることは『受粉』だそうだ。
気候条件に問題がない年は、中沢さんは2回受粉するそうだが、
今年は3回行った。
ずっと脚立で上を向いて、漏れがないように、
畑の、すべての桃の木に行う受粉作業は、熟練を要し、首が疲れ、
相当根気の要る作業だが、それを中沢さんは今年3回行ったそうだ。(注2)
(注2)桃のうち白鳳は、自家受粉で、人の手で受粉する必要がなく、
白桃は、受粉作業をしないと実がならないそうだ。
中沢さん:「(今年)受粉の手を抜いてしまった人はひどい。」
この丹念に受粉作業を行うことが、異常気象の影響を極力少なくし、
例年と変わらない収穫をもたらしてくれる。
一般には受粉作業は一回だけで、農家が老齢化して2回、3回とは
できないという現状もあるようだ。
今年の受粉は、4月12日~19日にかけて行われた。
一つ一つの花が受粉しているかいないか、目に見えないだけに
精神的な圧力があると中沢さんは言う。
桃の花が、開花しているのは10日間くらいで、
その時晴天が続き、遅霜もなく温度が高めだと好条件だそうだが、
あまりにも寒いときは、未明に畑で火をたくことがある。
1反(約992㎡)あたり8箇所で行い、空気の対流を起こして
霜が降りないようにさせるそうだ。今年も一回行ったという。(注3)
(注3)受粉するときは温度が12℃くらいないとだめで、
遅霜で凍ると組織が破壊されてしまうそうだ。

<約50年有機農業を続けているが、虫の害はなくならない>
土作りを長年続けていると、病害虫にはやられなくなるという話があるし、
中沢さん自身も講演会などに行くとそういう話を聞くことがあるが、
そんなことはないと中沢さんは今回何度も断言されていた。
そして、畑の一部で実際にアブラムシの害にあっているところに
案内してくれて、私たちもその木を拝見した。
それでは、中沢さんはどのように虫害などを防いでいるのかというと、
毎日毎日畑の隅々まで見て回って、問題があるときは除虫菊の成分や、
木酢液、乳酸菌などを使って虫を寄せつけないようにしているそうだ。
袋かけも、病気や、虫の害から防ぐ重要な作業で、
収穫が近づいてきて、袋を取る前に除虫菊で、木を消毒し、
袋を取ったら木酢液を散布する。
これをすることで灰星病などの病気を防ぐそうだ。
雨が多いときはもう一度、木酢液を散布する。
まさに念には念を入れるきめの細かい作業が続く。

<中沢さんの桃の木は、白樺みたいに幹が白い>
数年前に伺ったときにはなかったこととして、
中沢さんの畑を見ていて気づいたことが一つあった。
それは桃の木が白樺みたいに白いこと。なぜなのだろうと疑問がわく。
この木の白さについて、皆、疑問があったらしく誰からともなく質問が出た。
中沢さん:「実はねぇ。硫黄分の多い入浴剤を2000倍に薄めて
今年の1月に使ったんだ。硫黄は殺菌力が強いから、
木についているウィルスの胞子の密度を下げる働きがあるんだ。」
「有機農法で認められている石灰硫黄合剤というイオウの殺菌剤も
あるけれど、化合物がいろいろあるのでこれを使うことにした。」
イオウ成分の漂白作用が、木を白くしていたらしい。
社員: 「中沢さんのそのような発想はどこから出てくるんですか?」
中沢さん:「風呂に入っているときに思いついてねぇ。そこで石和温泉に
問い合わせしてみたら有ったので使うことにした。」
まさに四六時中、中沢さんは桃のことを考えている。

ブログ筆者KT
(後編に続く。)
![]()