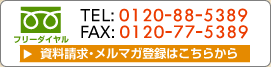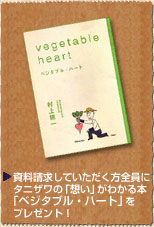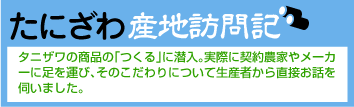2010年9月 萩原さんへの産地訪問
こんにちは、新入社員の市原です。
今回は、農薬や化学肥料を使わずに野菜を育てている、
長野の萩原さんを訪問しました。

萩原さんは、農業をされるようになるまで、
営業の仕事をしていたこともあって、
とてもお話が面白く、すぐに引き込まれてしまいました。
まず、萩原さんが見せてくれたのは、これです。

これは、畑の土壌に含まれる成分を分析する器材だそうです。
萩原さんは、畑ごとに土壌を調べ、
土壌の状態からそれぞれの作物に必要な成分を考えて、
どのような肥料を与えるかなどの計画を立てるのだそうです。
次に、萩原さんは、このような図を描いて、
農業の基本についてお話してくださいました。

大切なのは、「物理性」、「生物性」、「化学性」、「その他」。
牛糞、キノコの菌床くずなど、
使うと「良い」とされるものはたくさんありますが、
これさえあれば野菜が元気に育つ!
といったものは1つもないのだそうです。
それぞれの資材(牛糞、キノコの菌床くずなど)が土などに与える影響を
「物理性」、「生物性」、「化学性」、「その他」
の4つに分けて考えると、
1つの資材だけで、この4つを満足させることができるものはないので、
1つ1つの資材をどのように組み合わせるのかが重要なのだそうです。
萩原さんは、一般的に「良い」と言われているもの(例えば、酢)を、
○何故良いのか?
○何にいつどのように働くのか?
その仕組みを理解した上で活用しています。
こちらが、萩原さんが野菜を育てている畑です。

農薬を使わずに、虫から守るために様々な工夫をしています。

葉を見ると、今足りていない養分が分かるのだそうです。
萩原さんの話を聴き、
これほど緻密に計算して野菜を育てるものなのか・・・と、感嘆しました。
農業に改めて興味を持てた1日でした。

萩原さん、どうもありがとうございました!
![]()
2010年7月 吉沢さん・榎本さんへの産地訪問(後編)
前編より
後編は、榎本さんです。
榎本さんには、冬から春にかけて、ハウス栽培のトマトを出荷していただいています。
榎本さんは、大変勉強家で知識が豊富な方なので、今回もお話を伺うのを楽しみに訪問しました。
 こちらが榎本さんのハウスです
こちらが榎本さんのハウスです
まず、着いて早速案内していただいたのが、トマトのハウスです。
今は、一通り栽培が終わって、次のシーズンに向けて、土壌に手を加えているところでした。
籾殻やカニ殻、ぬかなどを畑に撒き、さらに良い菌を水で薄めて撒いているそうです。
そして、太陽熱で土の温度を上げることで、悪い菌を殺し、良い菌のみを繁殖させているということでした。
 籾殻がこんもり
籾殻がこんもり
 菌がいたるところに繁殖!
菌がいたるところに繁殖!
 熱く語ってくれる榎本さん
熱く語ってくれる榎本さん
その他、膨大な知識や榎本さんが今の農法をするようになった経緯をお話いただきました。
その中で、印象的だったのは、有機農法についての榎本さんの見解です。
最近、有機肥料を使っての農業がもてはやされていますが、単に有機肥料を使っていればいいということではないということでした。
なぜなら、有機肥料は分解が大変遅く、10年前に畑にいれた肥料の栄養分がようやく効いてくるものだからだそうです。
なので、畑の土が良くなってくるのは、有機を始めてから最低10年はかかるということ。
つまり、今の有機JASで定められている、3年間以上の有機栽培という基準は本当の意味では適していないということでした。
昔も10年やってみて畑が良くなると言われてきたそうなのですが、具体的に土壌の分析などを進めている榎本さんからお話を聞くと大変納得できる内容でした。

色々な勉強会でも引っ張りだこという榎本さん。いつも最新情報を仕入れていらっしゃるので、また来年もお話を伺いにいけたらと思っています。
<訪問を終えて>
今回も、大変ためになるお話をお二人から伺うことができました。
そして、やはり伝わってきたのが、高品質の野菜を作ることへの情熱です。
食べてもらう人たちの健康を考えたその想いを、自分も伝えていけるように頑張ろうと思いました。
では、最後にお忙しい中、時間を割いて貴重なお話をしていただいたお二人に感謝をして、今回のレポートを終わりにしたいと思います。
今回もどうもありがとうございました!これからもおいしい野菜をよろしくお願いします!!
![]()
2010年7月 吉沢さん・榎本さんへの産地訪問(前編)
どうもこんにちは。
ランチブログでお馴染みの堀口です。
今回は、7月の上旬に埼玉県の吉沢さんと榎本さんのお宅へ伺ったときの様子をレポートいたします!
まず、訪れたのは吉沢さんの畑です。
吉沢さんは、冬場は三浦大根やほうれん草など、品質の高い人気の野菜を毎年出荷してくれています。
今の時期は、とうもろこしがメインとなり、獲れたてのあま~いとうもろこしをたくさん送って下さります。
今回、訪れたのはちょうど、そのとうもろこしの出荷直前でしたので、とうもろこしについて話を伺ってきました。
 辺り一面がとうもろこしの広い畑です。
辺り一面がとうもろこしの広い畑です。
 こちらが吉沢さんです
こちらが吉沢さんです
とうもろこしがぐんぐん育ってきていて、宝の山といった感じですが、やはり虫の被害がなんといっても悩みの種ということで、その対策についてお話しを聞きました。
吉沢さんは、完全無農薬で野菜を育てていますので、農薬に頼った防虫対策はしていません。
基本的には、健康的な育て方をすることで、虫を寄せつけない強い野菜を育てているのですが、どうしても虫に食われる部分は出てきます。
そこで、今年は2点新しい取り組みをしたとのこと。
1つ目は、虫はどうやら穂先から齧る習性があるようなので、穂先を刈り取ってみたということです。
ただし、全てを行うのは難しいので、畑の端の部分を行ったそうです。
 穂先を見てみると
穂先を見てみると
 あ、虫だ
あ、虫だ
 穂先を刈ってみました
穂先を刈ってみました
上からのぞいてみると
 通常はこんな感じですが、
通常はこんな感じですが、
 齧られるとこのように...
齧られるとこのように...

今年初めて行ったそうなので、効果はどの程度かわからないそうですが、仮定が正しければ今年のトウモロコシに如実に現れるハズ。楽しみです!
そして、もう1点はトウモロコシの植える間隔を広げたということです。
畑に密集して植えれば、その分収量は増えます。
なので、普通の農家さんであれば、収量を増やそうとたくさん植えたくなるもの。
そこを吉沢さんは「たくさん密集して、病気や虫の被害、風で倒れる危険が増すよりも、悠々と育てて、一つ一つが立派なものとして獲れた方が、自分にとっても食べる人にも良い」と考え、そのような措置をとったそうです。
長年経験を積んできた、吉沢さんならではの発言だと大変感心しました。
流石です!
 人が余裕で歩けるんです
人が余裕で歩けるんです
なっているトウモロコシもこのような立派なもの。

今年も大変期待が出来そうです!
 試食もいただきました!甘かったです!
試食もいただきました!甘かったです!

今回も色々と野菜についての細かい話を伺うことが出来ました。やはり長年積み重ねてきた経験からくる目のつけどころはやはり違います。今は、息子さんとともに畑仕事をしているそう。日本の農業のためにもぜひその知識と技が継承されていって欲しいと願っています。
というわけで、前編はここまで。後編に続きます。
![]()
桃農家中沢農園訪問記(後編)
今回は、桃農家の中沢義直さんを紹介したいと思います。
中沢さんは、毎年美味しい桃を出荷して下さっています。
6月5日(土)に、中沢さんの桃の生産地、山梨県笛吹市を訪問しました。
以下の文章は、今回参加した社員のレポートです。
前編と後編に分かれた長編となっていますが、ご覧になってみてください。
今回は、後編です。
<お客さんの、三つの満足のために、本物を食べてもらいたいために桃を作る>
中沢さんは四六時中桃のことを考えていると先ほど書いたが、
正確には桃を食べるお客さんのことを考えている、
といったほうがよいかもしれない。
一般市販の桃は、糖度は10度から11度くらい。
雨の多いときは10度以下になってしまう。
中沢さんの桃は、雨の多いときでも13~14度になる。
中沢さん:「どんな天気のときでも(糖度は)14度以上欲しい。
さらに2度高いと味が違う。」
どうやら中沢さんの、糖度の目標は16度以上というかなり高いレベルだ。
中沢さん:「人の心を動かすのは難しい。人の心をつかむのは難しい。
それができたらすばらしい。それが信頼関係。」
決して派手なことではなく、50年間毎年堆肥を入れて続けてきた土作り、
剪定(せんてい)、管理、適正な量、そのような要素が総合的に絡んで
糖度が上がる。
天候をはじめとする外的条件を言い訳にせず、
地道な日々の積み重ねがお客様に感動を与える桃作りにつながる。
中沢さん:「届いて箱を開けたときの立派さに満足、
持ってみてずっしりとして満足、食べてみてそのおいしさに満足、
その三つの満足をお届けしたい。」
中沢さんの信念ともいえるこの言葉は、以前にも聞いたことがあるが、
そのために行っている様々なことを改めて伺いずっしりと重さを感じた。
白鳳、白桃の木を拝見し、その台木となる山桃の木を見ながら話を伺っていたら
もう午後の7時半近くになり、笛吹の盆地は薄墨のようなヴェールに覆われていた。

<奥様の、心づくしの手料理の歓待>
お宅に戻ると恒例の奥様の手料理が私たちを迎えてくれた。
近くで採ってこられたタラの芽のてんぷら、タレの味噌が絶品の茄子の料理、
カブのお漬物、そして中沢さん宅の名物、巨大なぼた餅や、お鮨などなど。
中沢さんの忙しい時間を割いての話や、いつも上品な奥様のおもてなしの心に触れて、今年も一人でも多くのお客様にこの本物中の本物の桃をお届けしたいと決意を新たにして、中沢さん宅をおいとました。

<追記-桃栗三年柿八年>
今年の新入社員と一緒に、産地訪問研修もかねて中沢さんのお宅にお邪魔したが、3人それぞれ個性が出ていてよかった。
最初に中沢さんの、尼子家の話のきっかけになったH君。もう少し落ち着きが欲しいが、よく言えば行動的。サッカーで言えば得点王を争うタイプ。中沢さんにもどんどん質問をし、最後には中沢さんに「オーイ島根、聞いているか」といわれていた。
一方寡黙なI君。帰ってきてから書いた訪問研修のレポートは見事に要点を押さえていた。
紅一点のIさん。夕食のときに奥さんが作ってくれたカブのお漬物が気に入って「とても
おいしいですう。」という感激の声に実感がこもっていた。共感力や、味覚に優れているのではないかと感じさせる。
畑の中で中沢さんがおっしゃったこんな言葉が思い出された。
中沢さん:「桃は、3年で実がなるようになる。その後5年目、6年目でよい木かどうか判定し、淘汰すべきものは淘汰する。君たちも、まずは、3年は当たり前、その後5年目で、ちゃんと会社に残れるようにしないとね。」
ソフトな言い回しだが、内容はなかなか厳しい。
5年後3人とも良い桃の木のように育っていて欲しい。

ブログ筆者KT
![]()
桃農家中沢農園訪問記(前編)
今回は、桃農家の中沢義直さんを紹介したいと思います。
中沢さんは、毎年美味しい桃を出荷して下さっています。
6月5日(土)に、中沢さんの桃の生産地、山梨県笛吹市を訪問しました。
以下の文章は、参加した社員のレポートです。
前編と後編に分かれた長編となっていますが、ご覧になってみてください。
今回は、前編です。
<一年に一度しか試せない>
うす曇の天候の中、私たち一行7名は、中央高速を車で下って、
午後4時半頃に山梨県笛吹市(旧一ノ宮町)にある桃農家の
中沢義直さんのお宅に到着した。
奥様の出迎えを受け、お宅で少し待っていると、
程なく中沢さんが畑から戻られた。
数年前にもお会いしたが、健康的に日焼けして、
笑うと歯並びのいい白い歯が印象的な人だ。
改めて、自己紹介をすると、恒例にもなっているが、
新入社員(今春入社の3名)の出身地を興味深く聞かれた。
中沢さん:「この中に地方出身者はいるかな?」
3人のうち島根出身のH君に白羽の矢が当たる。
中沢さん:「島根といえば尼子家だ。島根の尼子家といえば、
『我に七難八苦を与えたまえ』
と言った武将がいたなぁ。なんと言ったっけ。」
ここで、歴女(注1)ならぬ歴男のT部長が、
「『山中鹿之助』ですね。」とやや控えめに答える。
(注1)歴女(れきじょ)は、歴史好きの女性を指す造語。
中沢さん:「そうそう。山中鹿之助だ。」
(ふむ、打ち合わせなしにこの二人の会話はすごい・・・ブログ筆者)
という話になり、昔の人はそこまで言って自分を厳しいところに
追い込んでことに臨んだが、今の人間は昔の人に比べて軽くなってきた
という中沢さんの現代人評がしばし続いた。
そのような話のプロローグから、最近の桃作りの本題に話が進んだ。
もう50年農業を続けている中沢さんが、
最近は今までの勘や、経験が通用しないとのこと。
ベテランの中沢さんも最近の気象の変化には困惑されているようだ。
中沢さん:「(試したいことがあっても)一年に一度しか試せないんだ。」
この一言に、果樹園農家としての中沢さんの思いと、常に前向きな向上心を感じる。

<今年の桃栽培について>
今年は、中沢さんによると、1月、2月の気温が高く、
通常桃の開花は4月10日頃なのに3月下旬に花が咲いてしまったそうだ。
4月になると、今度は冬に逆戻り、遅霜があったり、氷が張ったりした。
5月は、気温が乱高下して10℃から25℃の温度差があった。
日照が少なく、生育が遅れたとのことだった。
このような、いわば異常気象のときに中沢さんが
一番気をつけることは『受粉』だそうだ。
気候条件に問題がない年は、中沢さんは2回受粉するそうだが、
今年は3回行った。
ずっと脚立で上を向いて、漏れがないように、
畑の、すべての桃の木に行う受粉作業は、熟練を要し、首が疲れ、
相当根気の要る作業だが、それを中沢さんは今年3回行ったそうだ。(注2)
(注2)桃のうち白鳳は、自家受粉で、人の手で受粉する必要がなく、
白桃は、受粉作業をしないと実がならないそうだ。
中沢さん:「(今年)受粉の手を抜いてしまった人はひどい。」
この丹念に受粉作業を行うことが、異常気象の影響を極力少なくし、
例年と変わらない収穫をもたらしてくれる。
一般には受粉作業は一回だけで、農家が老齢化して2回、3回とは
できないという現状もあるようだ。
今年の受粉は、4月12日~19日にかけて行われた。
一つ一つの花が受粉しているかいないか、目に見えないだけに
精神的な圧力があると中沢さんは言う。
桃の花が、開花しているのは10日間くらいで、
その時晴天が続き、遅霜もなく温度が高めだと好条件だそうだが、
あまりにも寒いときは、未明に畑で火をたくことがある。
1反(約992㎡)あたり8箇所で行い、空気の対流を起こして
霜が降りないようにさせるそうだ。今年も一回行ったという。(注3)
(注3)受粉するときは温度が12℃くらいないとだめで、
遅霜で凍ると組織が破壊されてしまうそうだ。

<約50年有機農業を続けているが、虫の害はなくならない>
土作りを長年続けていると、病害虫にはやられなくなるという話があるし、
中沢さん自身も講演会などに行くとそういう話を聞くことがあるが、
そんなことはないと中沢さんは今回何度も断言されていた。
そして、畑の一部で実際にアブラムシの害にあっているところに
案内してくれて、私たちもその木を拝見した。
それでは、中沢さんはどのように虫害などを防いでいるのかというと、
毎日毎日畑の隅々まで見て回って、問題があるときは除虫菊の成分や、
木酢液、乳酸菌などを使って虫を寄せつけないようにしているそうだ。
袋かけも、病気や、虫の害から防ぐ重要な作業で、
収穫が近づいてきて、袋を取る前に除虫菊で、木を消毒し、
袋を取ったら木酢液を散布する。
これをすることで灰星病などの病気を防ぐそうだ。
雨が多いときはもう一度、木酢液を散布する。
まさに念には念を入れるきめの細かい作業が続く。

<中沢さんの桃の木は、白樺みたいに幹が白い>
数年前に伺ったときにはなかったこととして、
中沢さんの畑を見ていて気づいたことが一つあった。
それは桃の木が白樺みたいに白いこと。なぜなのだろうと疑問がわく。
この木の白さについて、皆、疑問があったらしく誰からともなく質問が出た。
中沢さん:「実はねぇ。硫黄分の多い入浴剤を2000倍に薄めて
今年の1月に使ったんだ。硫黄は殺菌力が強いから、
木についているウィルスの胞子の密度を下げる働きがあるんだ。」
「有機農法で認められている石灰硫黄合剤というイオウの殺菌剤も
あるけれど、化合物がいろいろあるのでこれを使うことにした。」
イオウ成分の漂白作用が、木を白くしていたらしい。
社員: 「中沢さんのそのような発想はどこから出てくるんですか?」
中沢さん:「風呂に入っているときに思いついてねぇ。そこで石和温泉に
問い合わせしてみたら有ったので使うことにした。」
まさに四六時中、中沢さんは桃のことを考えている。

ブログ筆者KT
(後編に続く。)
![]()
← 前のページ |