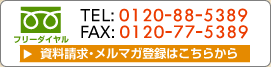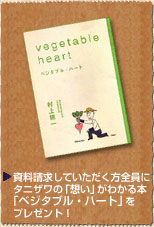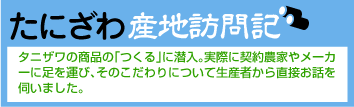今年も伺いました! 千葉県 小笠原昌憲さん
どうもこんにちは!
久々の産地訪問ブログです。
5月に訪問してまいりました、
千葉県の養鶏家、小笠原さんのことを
お伝えいたします。
タニザワへ入社した3人の新入社員とともに
行ってまいりました。
小笠原さんは、このブログでも何度か登場していますが、
千葉・大多喜町で養鶏を行って、
タニザワへは有精卵を出荷してくださっています。
ファンのお客様も多い、人気の卵です。
小笠原さんの卵の詳細は、2008年10月の産地訪問ブログを
ご覧いただければと思います。
今回も小笠原さんは、
自身の卵のこと、鶏の飼育で苦労されている点、
今後の農業のことなど、熱く語ってくださいました。
新入社員も熱心にメモをとって、質問をしていました。
鶏舎を見学させていただいた後は、
小笠原さんの卵の食べ比べを行いました。
産みたてのものと、産んでから1週間経ったものを
食べ比べたのですが、しばらく経ってからのものの方が、
卵自体にしっかりと味がついていて、
とてもおいしかったです。
またゆで卵や温泉卵など、いろいろな食べ方で
試食させていただきました。
最後は小笠原さん自身で建てた自宅に伺って、
2時間ほどお話をさせていただきました。
今回の産地訪問もとても勉強になりました。
これからも小笠原さんが一生懸命つくった卵を、
精一杯販売してまいりたいと思います。

餌の説明をする小笠原さん。手前は弊社新入社員。

産みたての卵を集荷させていただきました。

小笠原さん、どうもありがとうございました。
![]()
今年の桃は・・・?

こんにちは、久々の産地訪問ブログです!!
6/6(土)に若手社員を中心に、山梨県笛吹市の生産者、中沢義直さんを訪問しました!!
中沢さんは、桃、柿、ぶどう、プラムなどの果樹を中心に栽培しています。
中でも、夏の桃は絶品で、中沢さんの桃を心待ちにしている方もたくさんいらっしゃいます。
ですので、今年の桃の状況を聞いてきました!!

実は、まだすももくらいの大きさ。
今年は、若木も順調に成長し、収穫も昨年を上回りそうです。
7月下旬頃~8月中旬にかけての収穫になるそうで、今から楽しみですね!!

袋がけした桃の木
桃はとても栽培の難しい果物で、一般的には20回以上の農薬が使用されるそうですが、
中沢さんは、1回も農薬を使わずに、無農薬で桃を栽培しています。
もちろん、1つひとつ手作業で、大変な仕事になります。
当日も、実の袋がけ作業の真っ最中でした。
2人がかりで朝から晩まで袋がけをして、1日に2~3本しか進まないそうです。
う~む、これは大変だ・・・。
中沢さんは、「買った人との喜びを共有できるものを作りたい」と、熱心に語っていました。
さすが、「桃のアーティスト」と呼ばれる中沢さん、高い志を持って桃栽培に取り組んでいることを感じました。
どうぞ、今年の桃にご期待ください!!
![]()
新鮮な卵の秘訣! 千葉県 小笠原昌憲さん
こんにちは。堀口です。
大変×2、永らくお待たせいたしました。
1年もの長い間、お休みをしていたタニザワ産地訪問記。
今月よりメンバーも入れ替え、ようやく本格的に再開いたします。
今まで以上に、生産者の方の工夫や考え方、どういった努力をされているのかなど、より密着してその想いをお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、気分を入れ替えて...、
タニザワの生産者の元へ実際に赴き、お話しを伺う、タニザワ産地訪問記の復活です!!(ぱちぱち)
今回からはお話を伺うのと同時に、少しでもお手伝いをさせていただき、体験レポート的な要素も織り交ぜて、お届けしたいと思います。
それでは、再開第1弾のはじまりです!
それは、ある9月の週末のこと。
私とタニザワ最若手のアキラ君で、千葉県の大多喜町へ出かけました。
渋滞に苦心すること5時間半。
日もとっぷりと暮れて、ようやく着きました。
1日目は、小笠原さん自らが建てたという自宅に泊まらせていただきました。
しっかりとした木でできているのですが、これが広いのなんの。
これを1人で建てたというのですから、本当にスゴイ!
そして、翌朝。
早速、鶏舎を見学させていただきました。
長屋のように、鶏の成長に合わせて仕切られています。

そして、こちらが小屋の中の様子。

平飼いなので、皆元気よく跳ね回っています!(すごい元気)
中には、アスレチックのように足場もあるんですね。
そして、地面を見ると所々にトウモロコシの芯やカボチャの皮が...。
「小笠原さん、これはなんですか?」
「これは、タニザワさんで余った野菜をそのまま餌としてやっているのさ。カボチャなんて、中身だけうまくつついて食べるんだよ。見てて面白いよー」
あ、確かにカボチャの形はそのままで中身だけくり抜いてある!へぇ~、賢いんですね。
こちらは、新しく入ってきたばかりのひよこ小屋の様子です。


ぴよぴよぴよの鳴き声とちょこまかと動く様子がとっても可愛らしい♪
ペットにヒヨコいいかも。
他の小屋にはない設備として、「コタツ」があります。


生まれたばかりのひよこは、自分でうまく体温調節ができないからだそうです。
あったかそうですね。
ちなみに、40日ほど成長した姿がコチラ。

随分と凛々しくなりましたね。
でも、鳴き声はまだひよひよなんです(笑)
餌やりも体験させていただきました!


ズタ袋に入れた餌を、竹でできた餌桶に入れるだけなのですが、意外とこれが難しい!
お手本で見せてくれた小笠原さんの動きは、まるでヒョイというような手際の良さなのですが、
素人の力では周りにこぼしてしまったり、いくつかある餌桶にうまく等分できなかったりと...。
回数を重ねるしかない!また来て今度はうまくできるようにしよう。(ウンウン)
その後には、卵拾いも体験させていただきました!
鶏は暗いところで卵を産む習性があるので、専用の小部屋が用意されています。

新鮮な卵はどことなくあったかい!そして、ツヤツヤしています。

こんなに拾えた!
そして、お仕事の後には、嬉しい嬉しい朝ごはん!
ベジタリアンでもある小笠原さん自家製のメニューを用意していただきました。

とっても豪華で、一つ一つの味がしっかりしています!
その中でも、新鮮な卵で作った温泉卵はやっぱり一味違います。
とっても食べやすいのですが、育て方はどこが違うのですか?
「そうだねぇ。餌には、米ぬか、トウモロコシ、魚粉、大麦、牡蠣殻、蟹殻、牧草粉末など、いろいろと配合を考えてるし、もちろん抗生物質や遺伝子組み換えのものは使ってない。
ただ、そうやって安全なものを餌としてあげていればいい、平飼いで育てればいい、というのではなく、いかにして品質の良い卵を安定的に届けるということ、これを1番に考えているね」
どういうことですか?
「うん。昔、お店をやっていたことがあって、やっぱりお店側としてはお客様に品質の良いものをいつも届けたいと考えているんだけど、農作物はそこまでうまくいかないことが多いから...。たくさん収穫できた時に一気に送ってきたり、逆に急に品切れになることもあったんだ。
まぁ、そこの事情を知っているから、いつも良い状態のものを届けることを心がけているね。」
そうだったんですかぁ。確かに、毎日小笠原さんの卵を食べている人にとっては、いつも手に入るというのが何よりも嬉しいことですよね。
何気ない会話に、小笠原さんのプロの養鶏家としての言葉を聞けたのは何よりの収穫でした。
そして、食後に出していただいたのは、今小笠原さんがはまっている「自家製甘酒」。
体にとってもいいんだよ。と作り方も教えてくれました。
おかゆに麹菌を入れて、一晩炊飯器で温めるだけ、という簡単なレシピ。
砂糖が入っていないのに、デンプンの甘みでとってもおいしい!
体も温まって、風邪をひいても吹き飛ばしてくれそうです。
冬場になったら、試してみることにします♪
そして、一息ついた後は、近くにある小笠原さんの田んぼに案内してもらいました。
こちらは、もち米の田んぼ。収穫まで、あとちょっとというところです。


そして、ここでは雑草取りを手伝わせていただきました。
ここで、地道に雑草を取らないと稲が養分を取られてしまうのと、来年もまた生えてくることになり手間がかかるからだそうです。

しばらく無心で雑草を抜く...。
気付けば、汗びっしょり。
真夏だったらもっと暑いんだろうな。
そして、いつしか時間もあっという間に過ぎて、帰る時間となりました。
最後に記念撮影をしてお別れです。

「また新しい人が入ったら連れてきなさい。」
ありがとうございます。またぜひ伺わせていただきます!
というわけで、1泊2日で産地訪問に行き、大変有意義な時間を過ごすことができました。
まだまだ掲載しきれない話もたくさんあるのですが、それはまたの機会にいたします。
それでは、再開編第1弾はこの辺で。
また、近日中にお会いしましょう。
![]()
調味料製造 徳島県板野郡上坂町 ヒカリ食品 島田光雅社長
左がヒカリ食品の島田社長です。徳島県で安全性とおいしさにこだわった調味料を製造しています。右は弊社代表の村上です。
今回ご紹介するのは、ヒカリ食品の有機ソースです。徳島県を流れる吉野川の近くにヒカリ食品の工場はあり、今回はその工場を見学してきました。
ヒカリ食品の工場では、太陽光発電の利用、工場内を循環する水のリサイクルシステムなど、環境への配慮を徹底しています。また、製造過程で生じた野菜くずは堆肥化し、自社の保有する有機認定圃場で柑橘類の栽培に役立てています。環境保全という面での企業としての姿勢は並大抵のものではありません。
もちろんそのこだわりは、ソース作りついても同様です。ポイントは「安全性」と「味」です。
一般にソースの原料にはりんごを使いますが、ヒカリ食品ではみかんを使っています。その理由は、安全なリンゴの確保が難しいためで、これまでの発想を転換しみかんを入れることを思いついたそうです。安全性が確認されているものを全国から探し出し、りんごを使ったソースにも負けない味のものを作り出しました。全ては安全性のためです。
また、製造後は6ヶ月間寝かせて自然なまろやかさを出します。一般には、タンパク質加水分解物や果糖ブドウ糖液糖などの添加物を加えて、人工的にまろやかさを出しすぐに出荷しますが、ヒカリ食品のソースはじっくりと熟成させ、ソース本来の味を追求します。
その結果、一般のソースの10倍もの材料費がかかってしまうのです。材料に一切の妥協はありません。
「本物の商品は本物の材料から生まれる」。これがヒカリ食品のモットーなのです。
(タニザワ通信06年11月号より)
写真左 野菜くずで作った堆肥を使い栽培した柑橘です。レモンや徳島南部にのみ生育するゆこうなどを育てています。
写真右 ヒカリ食品の商品ラインナップです。弊社でも扱っているケチャップや野菜ジュースも見えます。
![]()
稲作栽培 茨城県河内町 山本太一さん

生産者の山本太一さんです。不耕起栽培という特殊な農法で、無農薬でお米を栽培しています。
食欲の秋です。新米の入荷が始まり、お米がとてもおいしくなります。今月の産知直送は、タニザワが自信をもってすすめるお米「ほたる米」についてご紹介します。丁度ほたる米も今が新米の時期です。
茨城県河内町。千葉県との県境である利根川を渡ると、ほたる米の生産者山本さん親子が住む河内町が見えてきます。
山本さんが栽培するほたる米の特徴は、田を耕さずに育てる「不耕起農法」で栽培することです。この農法を駆使することで土壌の生態系を壊さずに、今や貴重になったメダカやドジョウなどと稲は共存して成長していきます。また、通常の田よりも地中が硬い状態のため、稲は必死に自分で根を土の中に伸ばしていき、通常の3倍もの根をもつことができるのです。そのため、台風に襲われても倒伏することのない生命力に溢れた強い稲に育つのです。
お米の味についても山本さんのこだわりがあります。一般の稲作農家は、お米の保管体積を小さくしようとするため、精米機で籾殻を取ってから倉庫で保管します。山本さんの場合は、食味が落ちるのを嫌って、籾殻がついたままで保管し1ヶ月に1回ずつ籾殻を取り除いていきます。またお米を入れる袋にも工夫を凝らし、光触媒をコーテイングした山本さん特注のものを用いています。この袋はお米の酸化を防ぎ、やはり味が落ちるのを防止するそうです。
無農薬栽培で食味も良質な山本さんのほたる米を食欲の秋に一度お試しください。
(タニザワ通信06年10月号より)


写真左 びっしりと実ったほたる米の稲穂です。
写真下 太一さんは今は現役を退き、写真左の息子 の文則さんが米作りを行っています。

写真 微生物と有機物を混ぜて作った液肥が入った ポットです。
![]()