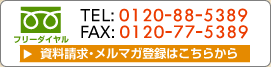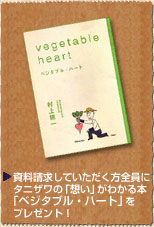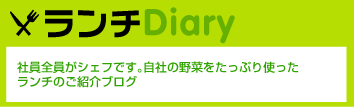2009年05月06日
豚角煮
☆本日のメニュー☆
――――――――――――
・豚角煮と大根の煮物
・トマト、インゲン、ベビーリーフのサラダ
・味噌汁
・きゅうり漬
・安曇野納豆
――――――――――――

――――――――――――
・豚角煮と大根の煮物
・トマト、インゲン、ベビーリーフのサラダ
・味噌汁
・きゅうり漬
・安曇野納豆
――――――――――――

今日のランチの時間です。
今日は豚角煮です。


なんと豪華な...
肉が、柔らかくて絶品です。
そんな角煮のルーツとは?
中国杭州の浙江料理(せっこうりょうり)の東坡肉(トンポーロー、トンポォロウ)が、沖縄県に伝わりラフテーとなり、長崎県では卓袱料理の東坡煮(とうばに)となった。
角煮は、ラフテーあるいは東坡煮から更に変化したもの、だそうです。
じゃあ、東坡肉はどんな料理かと言うと、栄の時代の詩人「蘇東坡(ソトンポウ)」ゆかりの豚肉料理で、茹でる・揚げる・煮込む・あんを掛けるという行程を経て余分な脂分を抜いたものだそうです。
「蘇東坡」が杭州の地方長官だったときのこと。ある日、東坡は客人を招待するため、豚のモモ肉(スネ肉)を料理しようと大鍋に入れておいた。
ところが、東坡が「書」に夢中になって筆を重ねているうち、いつしか3夜4日に及んだ。フト気がついて大鍋を見ると豚肉がすっかり水を吸って、膨らんでしまった。捨てようかと思ったが、これに味付けして食べてみると余分な脂肪が抜けて正に珍味となった。って本当かよ!?
4日も忘れてたものを、なんで食べようと思えたんだ...?
それに客人には何も出さなかったのか?来なかったとか?
というか、なぜ忘れたし!?
突っ込みどころは多いですが、角煮は美味しいから許す!
しかし「蘇東肉」、角煮と比べると、茹でて揚げて煮てあんを掛けるって手間かかってるなあ。
![]()