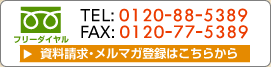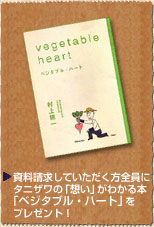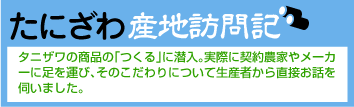野菜栽培 埼玉県さいたま市 榎本文夫さん
 写真中央が榎本さん。タニザワ社員にトマト栽培についてレクチャーしてくださいました。
写真中央が榎本さん。タニザワ社員にトマト栽培についてレクチャーしてくださいました。
タニザワの生産者のこだわりをお伝えする「産知直送」。今月号はトマトの生産者、榎本文夫さんのこだわりをご紹介いたします。
埼玉県さいたま市飯田新田。さいたま市とはいえまだまだ畑が多く残っているこの土地に、榎本さんのトマトハウスはあります。自宅の目の前にはびん沼川という川が流れており、私たちが訪れた3月末は土手沿いに並んだ桜の開花が丁度始まった頃でした。
今回の主人公である榎本さんは、25年以上トマトを栽培してこられたベテラン農家です。その榎本さんが目指すおいしいトマトとは、「甘みと酸味のバランスのとれた後を引く」そんな自然な味のトマトです。「甘さを強調しただけのトマトは、最初は目新しくておいしく感じるがそのうち飽きてしまう。俺が目指すのは毎日食べても飽きない、体にスーッと入っていくそんなトマトだ。」この榎本さんの言葉の中に、タニザワの野菜でトマトが一番人気である理由が含まれているのかもしれません。
榎本さんがおいしいトマトを目指す上で一番こだわっているのは、トマトに与える水です。トルマリン、硫黄石、ラジウム、そして日高昆布などの成分を水に添加して、なおかつ植物が吸収しやすいようにボイラーで温めてから潅水するそうです。「植物の95%は水分から出来ている。水にこだわるのは当然だ。」農学だけではなく物理学からも農業にアプローチするその姿勢は、榎本さんの農業の師匠から教わったといいます。「自然を相手にする農業は農学だけでは語れない。あらゆる学問と総合して考えなくてはだめだ。」
おいしいトマトをつくるために常に研究し、そして様々な工夫を凝らしている榎本文夫さん。おいしい野菜の裏には農家の並々ならぬ努力がありました。
(タニザワ通信06年4月号より)







![]()
干物製造 島根県出雲市 渡辺水産さん

渡辺水産さんの事務所です。出雲は暖流と寒流がぶつかる場所で、おいしい魚を獲ることができます。
今月は、島根県出雲市にある渡辺水産さんを紹介いたします。いつも渡辺水産さんからは、カレイやのどぐろなどの干物を送ってもらっています。先月の2月21日に、お伺いして工場を見学させていただきました。
今回の訪問で、干物の製造は、非常に奥が深く難しいもので、単純に、いい鮮魚をいい塩を使って干せば出来るというものではないのだということが、よくわかりました。
渡辺水産さんの干物の、一番の特徴は、やはり原料の魚の良さです。これにはいくつかのポイントがありますが、まず原料の買付けのノウハウが凄いと思いました。創業以来40年にもわたる長年のデータの蓄積で、いつの時期のどの船の魚の質が良かったかを、全部記録として残し、船を指定して魚を買付けるのだそうです。
もう一つのポイントは、魚の買付けの時期を、徹底的に"旬"にこだわるということです。長い期間取れる魚も、一番脂の乗ったおいしい時期のものしか、干物にしないのです。しかも年によって旬の時期がずれることもありますので、単純ではありません。ですから、魚の状態を日頃からチェックして、ここだ!というときに一気に買付けるのです。
これ以外にも、山陰沖の豊かな漁場、原料の状態で塩分濃度を調整する高度な技術、干物の乾燥時間の長さなど、おいしい干物の秘密は、お伝えしきれない程あります。
こうした、生産者のこだわりと努力で、新鮮で甘味と旨みがあり、しっかりとした歯ごたえの美味しい干物が出来るのだと思いました。今後も、是非、渡辺水産の"旬"の干物をお楽しみください! (タニザワ通信06年3月号より)
すぐ前には海が広がり、小型の船で
漁に出て少量ずつ獲り、新鮮なうち
に魚をさばくいていくそうです。
乾燥機の中で除々に魚を干していきます。 干物に使う魚をさばいているところです。 身が乾かないように数回に分けて少量ずつ さばいていきます。
左上から時計周りに「甘鯛の開き」 事務所には扱っている魚の種類と特徴がチ「のどぐろの開き」「カレイの一夜 ラシになって飾られていました。
干し」「アジの開き」です。
![]()
野菜・稲作栽培 滋賀県安土町 道尾芳孝さん、芳和さん
「有機農業は雑草との戦いだよ。」野菜・稲作農家の道尾芳孝さんは、自身の農業観についてこう語ってくださいました。
琵琶湖を間近に臨む、滋賀県安土町。織田信長が安土城を築いたことでも有名なこの地に、道尾さんの畑は広がっています。息子の芳和さんと共に、白菜・大根・水菜・カブを出荷していただいていますが、年末は降雪が多かったため、雪を掻き分けての収穫だったようです。
この琵琶湖周辺の土地は、戦後の干拓地で、農業には良い条件が揃っています。「畑の土は、琵琶湖の底土を使っているから栄養がたくさんある。冬場に霜柱が立たないのも、琵琶湖の湿気のおかげなんだよ。」道尾さんの農業のポイントは琵琶湖にあるようです。しかしこうもおっしゃっていました。「湿気は冬にはいいけど、夏場はとにかく大変。作物の病気が多くなるからね。」また、農薬を最低限に抑えるため、雑草の繁茂をいかに食い止めるかも頭を悩ませていて、それが冒頭の言葉につながっているようです。
元々、東京で働いていた芳孝さんは、琵琶湖の干拓に伴う入植者の募集を知り、奥さんと一緒に働ける仕事がしたいと、この土地で農家に転進しました。初年度は稲が大豊作でしたが、その後は減反政策などもあり、苦労されたそうようです。「最初は、1年のうち3ヶ月働き、あとは遊んで暮らせると思ったよ。しかし人生そんなにうまくはいかないな(笑)。」
琵琶湖の干拓と共に、試行錯誤しながら農業を続けてこられた道尾芳孝さん。琵琶湖が育んだ道尾さんの野菜を、私どもが責任を持って皆様にお届けしたいと思います。
(タニザワ通信06年2月号より)
芽キャベツはこんな風に育ち フェロモントラップ。これで害虫を
ます。 おびき寄せています。
![]()
野菜栽培 新潟県新潟市 小林勝さん、小熊八重子さん、山口次道さん
今月は、先月に引き続き、新潟県・旧白根市の生産者をご紹介いたします。旧白根市には、前号でご紹介した、ル・レクチェ生産者の大野さんの他に、きゅうり、かきのもと(食用菊)などを出荷している小林勝さん、夏場の茶豆(枝豆)の生産者、小熊八重子さん、そして毎年7、8月に、柔肌ねぎ(長ねぎ)を出荷している、山口次道さんの3名がいらっしゃいます。
昨年11月末にお伺いして、山口さんの案内で各農家を回りました。山口さんは、十数年前から、農薬使用を減らした栽培に取組んでいる若い生産者です。お話をお伺いする中で、「本当にいいものを作りたい」という熱意がひしひしと伝わってきました。柔肌ねぎの収穫時も、収穫したものを一切水洗いせず、一本一本丁寧に手でむいて出荷するそうです。水洗いをすると、手間なく簡単に泥を落とせるのですが、日持ちがしなくなるためです。しっかりとして日持ちの良い柔肌ねぎは、消費者の方への熱い思いから生まれる努力によってできるんだなあと、改めて感じました。
3人の生産者ともに、今回始めてお会いしましたが、やはりいいものを作りたいという思いを持った、とても信頼できる方々で、最終消費者であるお客様の元に、きちんとした状態で野菜が届いているかを、非常に気にかけていらっしゃいました。
今年も、小林さんのきゅうり、かきのもと、カリフラワー、セロリ、小熊さんの茶豆、山口さんの柔肌ねぎなどを、私どもタニザワが、責任を持って、皆様にお届けしていきたいと思います。 (タニザワ通信06年1月号より)
小林さんが栽培したセロリです。セロリは農薬を
大量に使う野菜ですが小林さんは極力農薬の使用
を抑えます。スジがなくセロリらしい味のする、
タニザワで好評の野菜の一つです。
小林さんが栽培したカリフラワーです。
同じく小林さんが栽培した食用菊のカキノモト
です。彩りが鮮やかでおひたしとしてよく食べ
られている花卉野菜です。
![]()
ル・レクチェ栽培 新潟県新潟市 大野松雄さん
今月の「産知直送」は、新潟の洋ナシ、ル・レクチェの生産者、大野松雄さんをご紹介いたします。大野さんは、新潟県の旧白根市(合併後は新潟市)で農業を営んでいますが、とても研究熱心な方で、一般的に農薬使用量の多い果物であるナシを、FFCという活性水を活用するなどの方法で栽培し、毎年、前年よりも農薬使用量を減らすよう努力しているのだそうです。
ナシは、枝を台木の株に接ぎ木して栽培をする果樹で、台木が何の木であっても、枝によって品種が決まります。すると、2つの品種のナシの枝を1つの台木に接ぎ木をするとどうなるのか?ちゃんと接ぎ木をした先からは、それぞれ違う品種の果実がなるのだそうです。なんと、大野さんのところには、1つの台木に4つの品種を接ぎ木し、4種類のナシが実る木もあるんです。不思議なものですね。
畑を案内していただいたあとは、新しく完成したばかりの、果物などの加工を行う作業場を見学しました。ここでは、傷物や小さくて出荷できないル・レクチェの加工などを考えているそうで、試作品のル・レクチェのペースト(ジャム)やコンポート(シロップ漬け)などを試食させていただきました。特に、このル・レクチェペーストは、ヨーグルトに入れると最高においしいと聞き、さっそく会社に帰ってから試したところ、社内でも絶賛の声があがりました。近日中に、このル・レクチェペーストやコンポートなど、新商品として、皆様にお届けできるかもしれませんので、ご期待ください。また、来年の大野さんのル・レクチェも期待したいと思います。 (タニザワ通信05年12月号より)
左の写真の右側は弊社代表の村上です。
実際にル・レクチェの木を見学させていただきます。
「私は中腰になりますが、妻が作業しやすいように、
木の高さは妻の身長に合わせてあります」と大野さん。
![]()